愛知県の作家・伊藤浩睦氏が、憲法記念日の5月4日、朝日新聞「声」欄に次のような投書を寄せている。
<私たちにとって、憲法はとても遠いものに思える。学校では、憲法上の権利を口にすれば、「憲法なんか生徒には関係ない。校則がすべてだ」と言われ、会社では、「社員である限り社則やノルマが最優先だ。憲法上の権利なんか関係ない」と言われた。庶民と憲法の関係なんてそんな遠いものだと思っていた>
数多い良識的な護憲論はほとんど立ち入ることがないとはいえ、およそ現時点の護憲論がなによりも直視すべき枢要の問題を剔る、これはとてもすぐれた発言だと思う。本当にその通りである。ふりかえってみよう。それぞれが日常的に帰属する「界隈」において普通の人びとの発言やビヘイビアを律しているものは、憲法に保証された人権尊重や思想・表現・行動の自由と無関係な、たいていはそれらを蹂躙する、その界隈の公然・非公然のルールまたは慣行にほかならない。
こうして学校では、「生徒らしい」服装や過剰な生徒指導の校則が若者の学校内外の自由を束縛する。職場では、過重なノルマ達成度や仕事態度を多面的に評価する査定の労務管理が、サラリーマンに「社員の掟」を内面化させ、彼らを萎縮させている。家庭では、なおしたたかに残る性と世代のジェンダー慣行が、それぞれの家族たち、とくに妻や母親にいいようのない鬱屈をもたらしている。社会運動の場でも、自治体は「中立」の名の下に運動にわずかでも「政治的」なにおいをかぎつければ、市民の営みに便宜を図ることをかならず拒む。ネットや公園に集うママ友の交友関係などでも、話題は「いやがられないように」無難なものに留めるという。
私の言う「界隈」に働くのは、まさに憲法の条文などかかわりない「界隈」独自のルールへの強力な同調圧力である。そして「界隈」の多数者は「空気」を読んでこの同調圧力に靡くだろう。構成員が憲法の条文に殉じて異議を申し立てるならば、その少数者はそれなりの受難を蒙ることになる。たとえば、学校の生徒が求めてやまない自由に固執して校則指導への反抗に転じるならば、サラリーマンが労働基準法を楯としてサービス残業を拒み休暇の自由な取得を主張するならば、労働組合員が労働組合法にもとづいて労使一体ムードの企業でストライキの必要性を訴えるならば、「対等の人格権」を内面化した妻が性別分業に居すわる夫を許さないならば、町内会の集まりで住民の誰かが信教の自由を唱えて神社への寄付の慣行に従わないならば、それらの勇気ある少数者は「波風立てるな」を旨とする多数者から「そっち系のひと」とみなされ、以降、無視され、つきあいで差別され、悪くすれば「界隈」から排除されてしまうだろう。排除されてもかまわない、その方が「すっきりする」場合もあるかもしれないけれど、多くの場合、一介の庶民は「界隈」から排除されてはやってゆけないのである。
こうしてニッポン2020年代では、憲法の保証する多様な個人の人権尊重、表現と行動の自由、労働基本権などは空洞化し、普通の市民の日常にまさにかかわりないものに堕しているのだ。この点を直視し、政治思想、政治運動論に留まらない「界隈」の民主化、すくなくともそこでの表現・発言の自由を達成する方途が探られなければ、護憲論は市民の生活に届かない。その方途の模索は容易ではないけれど、それぞれの「界隈」の少数者を「界隈」の境界を超えて横につなぐ営み、いわば外なる「界隈」の形成が、その出発点になるだろう。構想することができる、そしてすでに着手されてもいる例して、学校の枠を超える生徒会、Me tooの女性運動体、そして企業横断的な職種別・産業別労働組合の構築などをあげることができる。
「状況への発言」カテゴリーアーカイブ
プーチ・ダモイ!(2024年4月13日)
ロシアの女性たちがウクライナの前戦に駆り出された夫や息子たちを返せという果敢な街頭キャンペーン、「プーチ・ダモイ」をはじめている。NHKの「クローズアップ現代」で昨夜、その報道に接して言いしれぬ感銘を受けた。
彼女らは、動員は一定期間で交替するという当初の約束を容赦なく裏切られたのち、今やその要求を、民間人の動員の反対、ひいては軍事作戦をやめよという水準に高めている。このプーチ・ダモイに対しては、そして今のところ、権力も、従来の反戦運動に対するような過酷な暴力と逮捕の弾圧を控えているという。その理由は、権力側の政治アナリストによれば、前線の兵士たちは家族たちへの弾圧に憤り、戦線を離脱し、武器をもってロシアに帰ってくるかもしれないからだ。かつてのロアシア革命の勃発を連想させる、それは真に危機的な状況であろう。それに、もともと、家族の絆と国家への献身を結びつけて鼓吹してきたプーチンにとって、出征兵士の家族は敵視できないというジレンマがあるとも解釈される。
とはいえ、プーチンはむろん、その要求がわかりやすく、潜在的には広汎な共感をよぶプーチ・ダモイの広がりを放置できない。その担い手にはじわじわと「沈黙せよ」との圧力がかかっている。それに、NET世界では、第2次大戦中に出征兵士たちをじっと待ち続けたロシア女性を讃える歌「カチューシャ」を高唱しながら戦争協力を訴える「カチューシャ」運動も始まっている。数的な勢力はさしあたりこちらのほうが多分大きいだろう。そうして迫り来る弾圧とプーチン万歳・非国民弾劾の空気のなか、プーチ・ダモイの中心的な担い手、小児科医で一人娘の母であるマリア・アンドレエワは「怖い」と言う。だが、彼女は言葉を継いで、この時代に私が何もしなっかったと思い出すこと、後に娘に「あのときお母さんは何もしなかったの」を聞かれることのほうが「もっと怖い」と語るのである。
胸をつかれる。なんという勇気に支えられた平和と自由の希求だろう。ウクライナ防衛戦の暗澹たる風景のなか、プーチ・ダモイの広がりは、希望というもののささやかな発芽にほかならない。
春闘はどこへいったのか? 非正規春闘に注目せよ(2024年4月20日)
2024春闘はどうなったのか? 周知のように政府にも経団連にも言祝がれて大企業では満額回答、そればかりか組合要求以上の回答も相次いだ。4月18日の連合のまとめでは、3283企業の平均賃上げは定昇こみで5.20%、そのうちのベースアップ分はわかる企業の範囲では3.57%という。ストライキはもとよりなんらの紛争もないすんなりした収束であった。なんのことはない、大企業の「支払能力」は十分にあったのだ。もともと「5%以上」という連合の要求そのものが企業への配慮に満ちて低すぎたのである。
賃上げは組合員300人以上の1160社での5.28%に対して300人未満の2123社では4.75%である(以上、朝日新聞24.4.19)。中小企業の賃上げこそは現下の枢要の問題だが、そのためには、中小企業が人件費や材料費の上昇を大企業との取引価格に転嫁できなければならない。だが、いかにその必要性を政府が語ろうとも、元請けの親企業も、卸売業界も、そしてあえていえば消費者も、その転嫁、つまり製品・サービスの価格上昇を忌避し拒否する。人不足が死活問題になるまでに深刻化しないかぎり、中小企業での大企業並みの賃上げが難しいことは否定できないだろう。結局、24春闘の結果、企業規模別賃金格差は確実に拡大すると思われる。
では、労働者の4割近くを占め、累積する貧困者の中核をなす非正規労働者についてはどうか。大企業では、たとえ正社員組合であっても、今回は常用パートや嘱託職員はしかるべき賃上げを享受できよう。けれども、企業と直接の雇用関係がないとされる派遣労働者や臨時アルバイト、「自営」扱いのギグワーカーなどはその限りでない。それになによりも、未組織の非正規労働者の大群はさしあたり公式の春闘とは無縁のままなのである。
首都圏を中心にいくつかのコミュニティユニオン(CU)が協同する非正規春闘にこそ、私たちは注目すべきである。総合サポートユニオン共同代表・青木耕太郎の丁寧なレポート(『POSSE』56号:24年3月)を紹介しよう。それによれば、23年冬に発足した「非正規春闘実行委員会」には、全国16の個人加盟ユニオンが参加し、約300名の労働者が勤務先の36社に対して1律10%の賃上げを求めて団体交渉を行った。各地の非正規労働者の相談に根ざした行動であり、経団連前の街頭行動やストライキも展開された。その結果、靴のABCマート(パート5000人)では6%、アマゾン倉庫の派遣労働者には約4.3%、トンカツのかつやの都内店舗では8.9%(時給100円増)。スシローでは都内店舗で17%(時給200円増)の賃上げが獲得されている。私たちになじみのこうした店舗や作業場において低賃金で劣悪な労働条件のなか汗ばんで働く膨大な非正規労働者たち。その実像をわずかながら知る私は、彼ら、彼女ら自身の切実な行動による、未曾有の、しかし一般的にはあまりにささやかにみえる達成のもつ意味を心に留める。
そして今春、非正規春闘は、要求を①非正規労働者の10%以上の賃上げ、②正規・非正規雇用者の均等待遇(同一価値労働同一賃金)、③全国一律最低賃金1500円の実現と定めた。関西のいくつかCUや生協労連なども加わり、非正規春闘実行委員会の参加も23労組、約23万人に、交渉先企業も約120社、従業員総数で30万人ほどにまで増えた。宮城県では、みやぎ青年ユニオンが、仙台けやきユニオン、関西では、なかまユニオンなど4つのCUが実行委員会を形成し、関係企業への交渉をはじめ、街頭宣伝行動や地元経済界への申し入れを試みている。業種別共闘の動きもある。私学非正規教員たちは「私学非正規春闘」に着手し、広尾学園では8%の賃上げを達成した。介護労働者も「介護春闘」をはじめ、介護3法人に対して賃上げ要求を提出し、月7万円の賃上げが可能になる財政措置を求めて厚労省要請も試みている。
大企業での集中回答日の3月15日、実行委員会は「非正規春闘集中ストライキ」を企画し、その日、学習塾の市進ホールディングス、総合スーパーのベイシア、あきんどスシロー、英会話教室のGabaの4社に対してストライキおよび社前行動を実施した(朝日新聞24.3.14)。3月末にかけては15社以上でストライキを実施し賃上げを迫るという・・・。
こうした闘いの結果は、POSSE66号発刊の時点ではなお不明ではあれ、スムーズに大きな成果が得られると期待することはできないだろう。なお青木は、マスコミは首都圏や地元では非正規春闘に高い関心を寄せたと記しているが、多くの地方では労働運動によるスシローでの賃上げなどあまり報道されていない。ちなみに政財界は中小企業での賃上げを可能にする取引価格への転嫁の必要性を口にするけれど、生コンの標準価格を設定して中小生コン企業の支払を確保しようとした全国建設・運輸連帯労働組合・関西生コン支部を理不尽な刑事弾圧にさらしている。この未曾有の組合弾圧事件を関西以外の地域ではまったく報道しないマスメディアの労使関係のリアルに対する鈍感さは、非正規春闘の場合も同じである。ABCマートの非正規労働者――どれほど多くのなかまがいることだろう――の賃上げは、その意義においてトヨタ社員の賃上げと少なくとも等価なのである。
好個の文献、青木レポートは最後に、「25年春闘以降は、非正規労働者の賃上げ相場をつくること」をめざしたい、その際、「非正規公務員やケア労働者などがそのカギになるのではないか」と書いている。そのとおりである。青木も自覚しているように、非正規春闘の担い手たちの勢力もその影響力もなおきわめて限られたものに留まっている。それだけにいっそう大きな質量を秘めた結集を期待したい。
このところ非正規労働者に焦点を据えたいくつかの書物の刊行が盛んである。精粗はさまざまであるが、労働現場の実態把握は統計数値で済ませ、改善策は法的・行政的方途の提唱で終わる叙述も少ないように感じられもする。労使関係の視点が稀薄なのだ。そんななか、これまで異議申し立てを忘れていた若者たち自身が、労働の日々の鬱屈を顧みて、ストライキやボイコットや街頭行動のような、直接行動をふくむ労働組合運動をはじめることの意義ははかりしれない。ここに私は、日本では長らく不毛のままであった産業内行動・産業民主主義の再生の芽生えをみる。
民間委託の水道検針業務における労働協約拡張(2024年1月15日)
福岡市が民間委託する水道検針業務について、委託先企業すべてでパート検針員の最低時給を同じ水準にすることが決まった。自治労傘下の「福岡市水道サービス従業員ユニオン」が、市の東部と中部の委託先企業2社と結んだ労働協約を、歩合給の切り下げがあった西部をふくめて全市に適用するよう県に申し立てた、いわゆる労働協約の地域的拡張運動の結果である。これにより全市規模で、検針員は、最低時給1082円、一定の業務実績という条件を満たせば1420円~1605円 になり、労働保険・社会保険の加入が保障されるという。
これまでも地域的拡張の事例は11件みられたが、対象は正社員に限られ、民間委托の非正規労働者に適用されるのは今回がはじめてという(以上、朝日新聞24年1月6日)。
官・民を問わず委託・下請企業の非正規労働者の労働条件を包括的に下支えする労働協約の拡張は、今日もっとも労働組合運動に求められるアジェンダである。今回の達成は、民間委託企業の労働条件を公務員のそれと均等にする西欧型ユニオニズムの水準にはなお到っていないとはいえ、日本の労働界では画期的な第一歩の営みだ。その意義ははかりしれない。私には、ほとんど絶望的にみえる労働組合運の現状のなか、それは久方ぶりの希望の兆しだった。自治労は、これを先駆として、広汎な正規職員以外の働き手の労働条件の規制に突き進んでほしいと願うものである。
学校と教師――問題領域間の関連について(2023年10月23日)
文部科学省は最近、学校の諸相について、たとえば次のよう調査報告を発表している。
①2022年、小中学校の不登校は約22.9万人、いじめは約68.2万件、暴力行為は約9.5万件。いずれも過去最多であった(朝日新聞23.10.4)。不登校は子どもたちにとってかならずしも否定されるべき選択ではなく、いじめの増加は「認知」が網羅的になったことがその一因であるとはいえ、社会問題として浮上する「学校問題」が深刻化の一途を辿っていることは疑いない。
②教師は平日、小学校では11時間23分、中学校では11時間33分も働く。22年、残業時間は、小学校で月に82時間、中学校で100時間であった(NET情報)。教師の精神疾患の激増はすでに旧聞に属する。教職は現在、もっとも長時間労働の職業のひとつということができる。
③公立学校教師の労働組合組織率は、21年、30.4%、新規教員の加入は23.4%、日教組組織率は20.8%である。いずれも76年,77年このかた連続的な低下をみている(NET情報)。むろん組織率の動向は表層的な現象だ。明かなのは教師自身の発言力の著しい低下にほかならない。
このエッセイは、いずれも重層的な原因のある①②③それぞれの状況を立ち入って考察するものではない。私がここで問いたいのは3者の関連であり、その関連についてのマスメディアと「世論」(国民、あるいは子どもの保護者)、そして教師自身の認識である。それらをかりに「世論」と総称しておこう。「世論」はむろん①を深刻な問題と意識し、②は「先生の志望者を減らしもする」劣悪な労働条件として憂慮する。けれども、教師の過重労働が生徒たちとの豊かなコミュニケーションの時間や、学校でのトラブルに対する教師たちの協同対処のゆとりを奪っていることにはなかなか思い及ばない。すなわち②の労働問題が①の学校問題=社会問題が棚上げされるひとつの有力な原因であるという理解は、なお稀薄なのである。
だが、①②③の無視できない関連に関する「世論」について私がもっとも批判的に検討したいポイントは、現時点の日本における③教師の労働組合運動への徹底的な無関心にほかならない。今日では、「世論」のなかに、③ふつうの教員の発言権・決定参加権が②教師の労働問題のありようを左右するはずという認識すらすでにない。いや当の教師たち自身でさえ、「教師という労働者・職場としての学校」という観点をすでに失っているかにみえる。
およそ1980年代以降、もともと労働三権が剥奪されていたうえに、行政⇒教育委員会⇒校長と下降する管理体制が強化され、教員個人への人事考課が浸透するなかで、教師たちは教育実践と学校経営に関する連帯的な自治の慣行を次々に失っていった。「教育の荒廃」を日教組の「偏向教育」のゆえとする自民党右派の圧力もこれに棹さした。活発な討論の場であった職員会議はいまや管理者からの単なる伝達機構に堕している。教師間の助け合いの協同精神も風化し、教師たちは、個別の査定を怖れ、「私の教室に起こっている問題をむしろ同僚や校長に知られたくない」という気持から、社会のひずみの反映にほかならない学校問題に、誰に相談することもなく孤独に対処するようになった。教師の組合離れはそのひとつの結果である。要するにふつうの教師は今日、学校の労働についての主体的な発言権を失っているのだ。もし教師たちが学校においてみずから労働者としてのニーズや、日ごろ夢想する「教育の理想」の一端でも主体的な連帯行動に噴出させることができれば、それが②労働条件にも③学校問題=社会問題の改善にも大きな役割を果たすことができるのはいうまでもない。
たとえばアメリカ・ロサンジェルスの公立学校の教師たちは2019年、学校の民営化に抗議し、担当生徒数の抑制、新しいカリキュラム創造、極貧家庭の子弟への支援などの要求も掲げて「合法」とはいえないストライキを敢行している。そのピケ(!)には、保護者や子どもたちも加わった。そんな投企もありうるのだ。私たちの「先生方」の発言と行動のあまりの萎縮を、アメリカやイギリスで頻発する教員ストはふと顧みさせる。そういえば、今の教師たちは、「政治的偏向」とみなされるのを極度に怖れて、社会の暗部について生徒たちにみずからの見解を決して語らず、権力と闘う姿の背中を次世代に見せることはまずないという。
もういちどいえば、「世論」は、①の事象に現れる社会問題化した「学校問題」に危機感を抱き、②教員の過重労働を望ましくないと認識するけれど、ふたつは別個の問題であるかのように感じ、両者の関係には深く立ち入らない――日本の低賃金に関して労働組合の行動の不十分さ、たとえばストライキのまったき欠如を問うことがないのと同様に。そして③教育労働運動の衰退にみる教師の主体的な営みの萎縮については、いまや完全に関心の外にある。それは①にはもとより、②にさえも無関係であるとみなされている。
そうした多数の常識の帰結は、①も②も、その克服や改善の期待はすべて行政や法律に委ねられることだ。今の広義の教育問題の現状を規定しているのは予算決定を采配する政権の政策である。それゆえ、現状の改革を望む勢力の戦略は結局、政権交代、その方途は選挙での勝利に収斂するのである。どんな政権のもとでも、労働運動が学校を含むおよそ労働現場での労働者の発言権・決定参加権を与件とさせる、そんな欧米ではふつうのありようへの絶望が、すでに私たちの国の「空気」だからである。
いくらかふえんすれば、ことは教育・学校の問題ばかりではない。医療にせよ介護にせよ生活保護にせよ、事業体のサービスの質と量の不備・不足は、対人サービス職労働者の要員不足や低賃金や雇用の不安定や離職によって引き起こされている。その所以はそして確かに、予算、制度、法律など上部の利権関係や権力構造に求められる。それゆえ、今の日本に軍備拡張などのゆとりはない、広義の福祉に資金を回せという政治の場での追及はまぎれもなく正当であろう。だが、その政治的追及の熱量も、しかるべき労働条件とディーセントなサービスを求める現場の対人サービス担当者の連帯的な産業内行動(industrial action)、ときには叛乱によってこそ保証されるのだ。そうした労働運動は、利用者のニーズをみつめ続けることにおいて市民運動と連携することもできる。現時点の日本では総じて、この労働現場からの突き上げが欠けている。それゆえ、たとえば訪問介護ヘルパーが人権尊重的な介護のために一人の利用者にさきうる時間を延長する努力は、選挙のとき福祉を重視する政党に投票することに限局されるのである。
エッセンシャル・ワーカーとしての対人サービス職の人びとがますます増えてゆく時代である。そうした労働者は、日常的に、直接的に、仕事を続けてゆける労働条件と、公共サービスの利用者・受給者のヒューマンなニーズを汲む仕事の遂行を求める。そのために
は組合づくりの営みが不可欠となるだろう。「世論」はさしあたり寒々としているけれど、そう願うのは、いつまでも、私のような産業民主主義の信奉者のみではあるまい。
最低賃金と貧困(2023年7月24日)
パーソナル総合研究所の調査によれば、「働くことを通じてしあわせを感じる人の割合」は、日本では49.1%で、主要先進国の70%台後半とくらべて極端に低く、世界18カ国中の実に最低という(朝日新聞23.6.26)。
私はくりかえし日本の労働状況を辛辣に批判してきたが、空しく感じもして、実はもう倦んでいる。だが、ときに、これだけは忘れまいと記しておきたいことが心によぎる。もちろん多少とも「他人」の労働と生活の貧困に無関心でない人にはご承知のことだが、みんなに広く知られていることだろうか、それは最低賃金と貧困の関連である。
フルタイム労働者の賃金の中央値に対する最賃額の割合(%)は、OECDの2021年の調査では、フランス61.0、イギリス56.9、ドイツ51.1であるが、日本では44.9にすぎない。その高低は、貧困率(世帯人数で調整した収入が中央値の半分以下の人の比率)とほぼ逆相関にある。また最近、慶応大学の山田篤裕教授にあらためて教えられたことだが、いちおうは貧困線未満の労働者のうち最賃額の1.1倍より低い賃金で働く労働者の割合は、04年の4割強から19年には約6割に高まっているという。山田は続けて、少なくとも最賃額を1015円にはすべきだと論じる。そうでなければ、短時間労働者が健康保険や厚生年金保険に入るには「週20時間以上働き、収入が月8万8000円以上」という条件があるため、月8.万円を時給に換算した時給1015円がなければ、いちおうふつうの生活のできる社会保険制度から弾かれてしまうからである(朝日新聞23.7.20)。
岸田内閣が仰々しくいう「最低賃金1000円を」なんて今さらである。朝日新聞など有力メディアは、貧困の実情などはよく報じるけれど、労働問題の最賃と社会問題の貧困との不可分の関連をよくわかっているのか心許ない。まして、そこに関わる人びとの労働運動、社会運動の実践には徹底して無関心である。猛暑のいま、携帯扇風機とスマホを手にして通り過ぎる「市民」に、最賃1500円を!と訴えるユニオンの営みこそ、まさに貧困との闘いなのだとわかっているだろうか。
付録のスナップは、我が家のさるすべり、近影、妻と愛用の伏見・鯱市のカレーうどん、節約した「王将」での夕食。




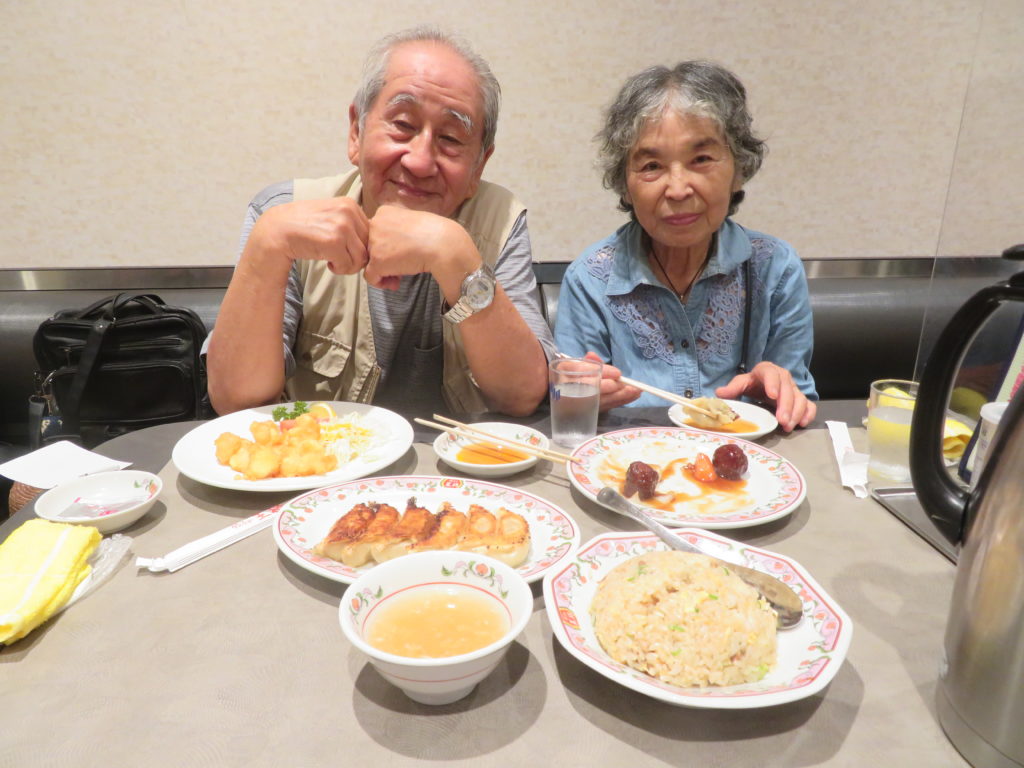
戦争の危機――問われるべき国民意識 (2023年6月16日)
戦後の日本人にとって憲法9条こそはすべての人倫の基礎である。幼少の頃からそう信じてきた私は80歳代半ばになったいまはじめて、日本は本当に戦争に巻きこまれるかもしれない、あるいは戦争を始めるかもしれないという不安にとらわれている。2015年安倍内閣によるアメリカに対する集団自衛権行使の約束と、岸田内閣による敵基地攻撃能力整備・軍備倍増の安保三文書の閣議決定を併せ考えると、専守防衛の原則をふみにじって日本が海外においてさえ軍事行動を起こす可能性は明かだからだ。それは過剰の危機意識でもたんなる杞憂でもない。

だが、いっそう不安なのは、ふつうの戦争のできる国への歩みに対する国民の危機意識の希薄さや欠如である。世論調査は時期や設問タームによって変動するとはいえ、2022年から23年初夏にかけて、敵基地攻撃能力保持については賛成が56%、反対が38%であり、しかも若い世代ほど支持率が高い(朝日新聞23.1.6)。「防衛力強化」に関する質問では賛成は68%、反対は23%(読売新聞22.11.6)。憲法9条を改正して自衛隊を軍隊と明記することについては、賛成51%、反対33%である。女性よりは男性のほうがはるかに賛成が多いことが印象的だ(朝日新聞22.7.4)。国民は増税に反対するけれども、軍事費大拡大には抵抗するわけではない。その背景にあるものは多分、実に80%の人が賛成するという、覇権主義的な動きを示す中国を「脅威」とみる(読売新聞22.11.6)おそらく過剰の警戒感であろう。
それにしても、少なくとも20%強から40%弱の国民はなお、以上の戦争準備に反対の立場である。問題は、この少数とはいえない反対勢力が、選挙運動以外の反戦・憲法擁護の社会運動を、力強い質量をもって展開できないでいることであろう。ここから思うに、いま諸組織のリーダー層は、1970年~84年生まれの40歳から50歳代前半のいわゆるロスジェネ世代である。91年~2001年の就職氷河期に社会に出たこの世代は、それからの生活の明暗が階層的にくっきり分かれる存在であるが、成功者も不成功者も、それぞれにその生活条件は自己責任とみなされるゆえに、厳しい選別のなか競争に生きてきた。その惰力は、連帯の労働運動や社会運動によって体制の構造を批判し、自己責任論を乗り越えてゆく発想をもたなかったことである。ロスジェネ世代は、その思想形成期にそのような連帯の運動の営みを経験したことも、みたこともないのだ。その世代が、今や、人びとが日常的に属する界隈――職場や地域や学校の保護者会や地方行政における小ボスである。この小ボスの卑俗な現実主義に支えられる慣行が、総じて強力な同調圧力を瀰漫させる。個人の受難を見過ごさず社会の構造的矛盾を指摘しようとする少数者は、KY、空気が読めないものとみなされ孤立させられることを怖れて黙り込むのである。職場での、労働組合の会議での、ボスの提案に対する批判の完全な欠如は、その典型的な姿にほかならない。
では、このロスジェネ世代の子どもたちである10代、20代の若者の意識状況はどうか。青年男女は一見、体制に逆らわず競争社会に順応するようにとの両親の説教を無視するかのようにみえる。だが、現時点の学校では、社会の構造的矛盾や日本近現代史の暗部については教えられ、学ぶことはもうほとんどない。そればかりか彼ら・彼女らが日常的に属する教室がすでに強力な同調圧力の界隈なのだ。社会や政治の深刻な問題を友だちに語りかける若者は変わり者の「そっち系」として疎外される。そんななか、若者の間では、およそ社会を批判すること自体が、自己責任や自分の努力不足を忘れて他を責めるはしたない行為と受け止められているかにみえる。「中立」の名目をひとつ覚えとする教師もまた、この傾向に棹さしている。学校では、街頭の市民団体のビラを決して受けとらないように「指導」しているという。
各地にみることができる、非正規労働者たちの、さまざまの被差別当事者たちの社会運動に私は希望を見いだす。だが、他の主要国とくらべれば、その厚みの無さ、若者参加の乏しさは否定できない。こうして私の日本の国民意識の評価は絶望に近づく。そしてこれ以上、私は議論を進めることはできないのである。
とはいえ、労働研究の眼から見れば、50代になっても非正規労働者のままであり、ひきこもりも増えているロスジェネの不成功者も、ブラック企業のいじめと収奪に翻弄される若者も、苦しみの根源は労働問題にほかならない。その根源への挑戦はひっきょう企業の枠を超えた地域別、産業別、職業別労働組合によってしか果たされないだろう。働く人びとが、自己責任論の虚妄性に気づき、多様な労働組合運動の営みをはじめる日がきっと来る。それが市民運動と連携して<非戦・当事者発言権・侵されない人権>を掲げる護憲運動の器にもなる。その確信を私はまだ捨てていない。
*(図版はマルク・シャガール「戦争」)
2023年春闘に思うこと(23年3月16日)
自動車、電機、重機械などの大企業の「春闘」で満額回答が相次いでいる。JAM幹部などはもう有頂天だが、それほど、それは寿ぐべきことだろうか。
今に始まったことではない。かつて日産自動車では満額回答が慣例だった。そもそも組合の要求そのものが企業とのひそかな合意のもとでつくられていたからだ。今年も、組合が経営側の意向に抗して交渉でがんばったというよりは、欧米では考えられないことだが、要求額が企業側との事前調整が行われていたため、すんなりと「妥結」したのではないか?ストの構えなんてはじめからなかったというのは、もう野暮なことだろうか。もともと要求水準が低すぎる。今の4%の物価高では、たとえ定昇込み3.8%で収束しても実質賃金の上昇は見込めない。せめて10%くらいの要求が当然ではないか。
連合や「識者」は、この満額回答が中小企業や非正規労働者の賃上げに波及することを期待している。しかり大企業正社員以外の労働者の賃上げこそが最重要の課題である。しかし、上の「期待」がほんものなら、連合傘下の大企業労組は、自社の取引先、とりわけ下請企業でのコストアップにみあう価格引き上げの容認をはっきり「要求」すべきであろう。そこで闘え。あるいは、いま真に意義ぶかい営み――非正規労働者を組織するいくつかの地域ユニオン・コミュニティユニオンが連帯して10%賃上げを求める直接行動を、財政的に、または組合員の動員をもって支援すべきである。それらができるか? できなければ、大手企業の春闘相場がどうあれ、実質賃金の確保は危うく、社会的な賃金格差と中小企業労働者と非正規労働者の構造化した低賃金は変わらないだろう。
NHKのすぐれたドキュメント(23年3月2日)
ひごろNHKの報道番組はあまりにジャーナリズムの神髄であるはずの批判精神を欠いていて失望させられるばかりである。ついでに言うと、アナウンサーがさよならと手を振る、「まるっと!」なんてばからしくないか。けれども、NHKの調査報道・ドキュメントについてはなお、取材の広さと深さにおいて必見の作品も少なくないように思われる。
例えば2月25日放映のETV特集「ルポ 死亡退院~精神医療 闇の実態」である。都立滝山病院において、多くは家族からも見捨てられた統合失調症などの入院患者は、看護者に嘲弄され、暴行され、苦痛を訴えればうるさいと縛られ、衰弱して死んでようやく退院できる。生活保護受給者も多いこうした患者たちは、虐待を知りながらも、こうした処遇の病院を「必要悪」とみなす地方自治体や保健所からも送り込まれているのだ。病院は生活保護受給者は入院費の取りはぐれがないので「歓迎」するという。厚労省も問われれば「プライヴァアシー」を楯にして個別事例の釈明には立ち入らず、空しい一般論を語るのみである。統合失調症はみずからの希望を語る能力も一切ないとされているのだろうか? 番組中やがて死を迎える高齢の患者は、弁護士に虐待を訴え、ここから出してほしいと泣きじゃくる。現代日本で最も完全に人権を奪われている人びとがまさにここにいる。なんという悲惨か。このような患者の棄民化は、滝山病院に限られないことも番組で明らかにされている。
思うに、判断力を欠くとされる精神病者といえども、みずからの意向が表明されるかぎり、非情の家族や医師の判断がどうあれ、強制入院されるべきではない。日本で精神病者の人権が尊重される度合いは、おそらく、他の先進諸国くらべて遙かに低いだろう。
ちなみに最近、ウクライナ戦争についても二つのすぐれたNHKスペシャルを見ることができた。ひとつは、開戦直後、欧米指導者たちの亡命の勧めを拒んでキーウイに留まり、勇気ある市民たちの自発的レジスタンスに励まされて抵抗戦に入ってゆくゼレンスキーら閣僚たちを描く「ウクライナ大統領府 緊迫の72時間」(2月26日)。「ウクライナはアメリカやNATOによってて空しい戦争を強いられている」という、一部「左翼」の判断の誤りを、この番組は教える。
今ひとつは、「なんのため闘うのか」がわからないまま「肉片」としてウクライナに送り込まれたロシア兵たちの、刑務所より非人間的な扱い、その戦意喪失と数多い脱走、そしてポーランドなどで一部脱走兵がプーチン支配を拒むロシア人を組織し、対ロシア戦のためにウクライナに送ろうとする試みなどを描く「調査報告 ロシア軍 プーチンの軍隊で何が?」(2月28日 再放映)である。なお息づく一部ロシア人たちの感性が感銘ぶかい。ロシア軍の内部崩壊ほど、いま世界から待たれていることはない。
イギリス公務員50万人のストライキ(23年2月4日)
2月1日、イギリスでは、学校教師10万人をふくむ多様な部門の公務員50万人ものストライキがあった。5000人以上のデモがウェストミンスターの官庁街をぎっしりと埋めた。学校の半分が休みになった。大英博物館もスタッフのストライキで休館となった。
昨年来、イギリス各地では、年10%ほどの物価高騰に直面して、鉄道や地下鉄などの交通機関、郵便局、港湾、郵便局などの労働者、ゴミ収集などの現業公務員、空港地上スタッフ、教師、救急隊員、病院や大学の若手スタッフなどのストライキやピケが相次いだ。要求はほぼ10%の賃上げである。とくに衝撃的だったのは、12月15-16日における国営医療の看護師たちの大規模な、ときに労働組合機能も果たす「王立看護協会」始まって以来初のストライキだった。
あえてさまざまの分野を列挙したのはほかでもない。この国のストは、地域、産業、職業ごとにきわめて分権的に始まり、その先駆的な行動が野火のように他の職場にに広がってゆくのが伝統だからだ。そこにはまた、労働者の生活を守るためにはひっきょうストライキしかないという、産業民主主義(端的には労働三権の行使)の不可欠性に対する断固たる確信が息づいている。思えばサッチャーは80年代半ば、10万人・1年間の炭坑大ストライキを「内部の敵」としてたたきつぶしたが、さまざまの分野で働く当時の坑夫の子や孫たちはなお、この「確信」をわがもとしているかにみえる。そして注目すべきことに、その思想は組織労働者だけのものではないようだ。BBCが伝えるサヴァンタ・コレムズの世論調査によれば、総じて国民の60%はこれらのストライキを支持している。看護師や教師のストライキへの支持はとくに高率であった。2月1日のTV報道のインタビューでも、デモ参加の教師たちはもとより、街頭の親や子どもたちも、ストライキの正当性を朗かに表明していた。
この50万人ストライキについて、日本のマスメディアは、毎日新聞やTBSがわずかにふれるのみで、総じて無視している。その立場は、インフレに伴う生活苦を打開するストライキというものの意義を顧みないように誘導しているとさえ思える。イギリスのストは、いま話題とされている「春闘」で賃上げがどれほどになるかの問題と無関係だろうか?、まさにここに関わるのではないか。まえにも私が論じたことだが、日本ではいったい誰が賃上げするのか? 労働組合の行動なくしても「温情的」な政府や経営者が賃金を上げてくれるのか? ここまで産業民主主議の思想を忘却している「先進国」はない。この忘却は、残念ながらマスコミ界だけではなく、労働界にも、野党にも、革新論壇にも、私が日頃敬愛するFBの「お友だち」のなかにさえ浸透しているかにみえる。しかし、だからこそ私は、昨年末に書き下ろした、先駆的にサッチャーと闘ったレジェンド、「イギリス炭鉱ストライキ(1984-85)の群像」の刊行を模索し続けている。
